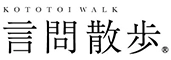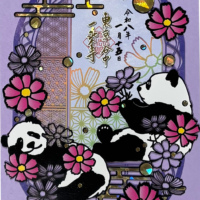朝顔に魅せられて
子どものころから親しんできた朝顔。実はその世界が、とてもクリエイティブだということをご存じでしたか?もともとはシンプルな花だった朝顔が、やがて品評会まで開かれるほどに。本記事では、そんな朝顔の歴史や、七夕との関わりなどをご紹介します。

江戸の人たちの心を掴んだ『変化朝顔』
1860年3月4日、世に言う「文化3年の大火」によって、現在の御徒町にあたりは更地と化し、その跡地にほかの植物と一緒に朝顔を植えてみたところ、面白い形の朝顔がたくさん咲いたと言います。初めは素朴な花で満足していた人々も、だんだん変わった形を追い求めるようになります。
その結果わずか数年で、下谷御徒町は見物客が大勢集まるような朝顔の名所と変貌を遂げたと言います。
多大な手間暇とお金をかけて技術を競う、とてもクリエイティブな世界ですが、珍しいものが大好きで、驚いたり驚かせたりするものも大好きな江戸の人たちが、これに心を奪われないはずはありません。お金をかけて作り上げた自慢の変化咲き朝顔は、江戸や大阪の各地で開催されていたコンテストである「花合わせ」に出品されるようになりました。そして、専門書も多数発行されるようになり、相撲の番付をまねた「花合わせ番付」等も出版されています。特に評価が高かったのが、入谷の植木屋成田屋留次郎が出版した「三都一朝」でした。江戸、大阪、京都、それぞれの地で出版された名花を編集しており、国立国会図書館にも収蔵されています。


七夕の縁起物
早朝から凛と咲く姿が美しい朝顔。太陽に向かってしっかりと蔓を伸ばし朝露が眩しい朝顔は、目覚めに見ているだけで暑い夏を乗り切る元気をもらえます。そんな愛おしい朝顔が日本に伝来したのは、奈良時代末期に遣唐使が中国から種を持ち帰った時だとされています。当時は花を楽しむのではなく薬剤としての効果が注目され種子を薬として利用していました。質の良い薬として日本にやってきた朝顔はとても高価なもので当時貴重な財産であった牛と交換するほどだったそうです。贈答品としても珍重され、朝顔を贈られたら牛を引いてお礼に行くほどだったとか。
種子に薬効があるとされ伝来した朝顔の生薬名は「牽牛子(けんごし)」といいます。この名前の由来は、七夕伝説の彦星の中国名である「牽牛(けんぎゅう)」からきているという説があります。その由来から、花が咲いた朝顔は、「彦星」と「織姫」が出会えたしるしとして縁起の良いものとされ、江戸時代は「七夕の縁起物」として珍重されました。朝顔の花の中心はかわいいお星さまの形をしていますよね。それも相まって現代では、花が咲いたら彦星と織姫が出会えたしるしだと言われ、恋愛運UPの縁起物とされています。
毎年7月6日から8日まで開催される「入谷朝顔まつり」も、七夕伝説にちなんでのことなのです。


「朝顔」 名前の由来
「朝顔」の名前の由来は「朝の容花(かおばな)」という言葉からきていると言われています。「容花」とは美しい花を意味する言葉です。もともと「朝顔」は朝に花が咲く植物を総称した名前で、その中には桔梗や昼顔なども含まれていたそうです。現代の朝顔が他の花と明確に区別されるようになったのは、江戸時代頃からと言われています。