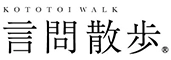根岸・鶯谷編

書道博物館
書道博物館
根岸・鶯谷の
歴史を知る歩きかた
旧陸奥宗光低
カミソリ外相と名をはせた陸奥宗光の邸宅。このお屋敷は海外事情に精通した長谷川武治郎が買い取り、幻のちりめん本がつくられていました。翻訳もライフがディオハーン(小泉八雲)などの当時の在日外国人が行っていました。挿絵は江戸浮世絵の流れを汲み、日本で初めての海外出版社と契約を行い、1900年パリ万博で金賞を受賞。「ちりめん本」は海外に多く影響を与え、非常に高い評価を得られている。
👣(徒歩2分)
円光寺
江戸時代(寛永2年、1625年)創建、400年の歴史を誇り、安藤広重の浮世絵にも描かれた名刹です。境内に咲く藤の花が有名で、藤寺とも呼ばれ、その名の通り4月から5月には藤の花がきれいに咲いています。またきれいに手入れされた境内では、藤の季節以外でもそれぞれの季節を感じることができます。通常座禅やヨガの会が定期的に催されれています。
👣(徒歩5分)
八二神社
明治5年、前田家がこの地に広い土地を買って邸と庭を作り、13代成泰様の隠居のため移り住んだといいます。根岸の「兼六園」と言われたものの、現在は一画に祀られていた祠が残るのみとなってしまった。しかしそれが八二神社である。大正13年前田家が敷地を分譲した際その土地が根岸82番地だったことが由来。実は子規庵も前田亭の敷地内にあり、前田家が借家としてかしていたという。正岡子規はここに引っ越した際、「加賀様を大家にもって梅の花」と詠んでいる。ホテルが並ぶこの街でここに兼六園があったとは思いもよらないが、当時の情景を想像する手掛かりは敷地内に暮らしていた子規の句に残る。
👣(徒歩2分)


子規庵
正岡子規は明治27年、旧前田藩広大な下屋敷の御家人用二軒長屋に明治27年から移り住み、古郷間松山から母と妹を呼び寄せ、子規庵を病室兼書斎と句会歌会の場として、多くの友人、門弟に支えられながら俳句や短歌を生み出していきました。子規の没後も子規庵には母と妹が住み、句会、歌会の世話を続けました。
庭からは上野の山を望むことができたそうです。子規没後100年を経て、子規庵の周囲は大きく様変わりしていますが、子規庵の縁側に腰ことりのすがたことりのすがたにかけて小園を眺めると、静けさと訪れる小鳥の姿にも当時の子規庵を偲ぶことができます。
👣(徒歩1分)
書道博物館
画家であり書家でもあった中村不折が40年にわたり集めた中国、日本の様々な絵画や書作品のコレクションを展示した専門博物館です。
殷時代の骨董や青銅器、仏像、文書等重要文化財となっているものが展示されており、書に興味のない人でも有意義な時間を過ごせる施設。不折の作品か関係資料を展示する中村不折記念館を併設しています。受付の職員の方が親切でとても感じがよいのも評判。収集物には重要文化財も多く、中国の青銅器、拓本などは素人目にも素晴らしいものが多い!見に来る人は少なく開いていますが、もったいないくらいの穴場。
👣(2徒歩分)
御院殿坂
寛永寺 輪王寺宮一品方親王は、第三世代から幕末の第十五世まで親王あるいは天皇の養子を迎え継承されてきました。当時はこの根岸に林王寺宮の別邸「御隠殿」があった。御隠殿の創建年代は明らかでないが、敷地はおよそ三千数百坪、入谷田んぼの展望と老松の林に囲まれた池を持つ大変優雅な庭園で、ここから眺める月は美しかったと言われている。
輪王寺宮は1年間のうち9ヶ月は上野に常在。その時は寛永寺本坊(現東京国立博物館構内)で公務に就き、この御隠殿は休息の場として利用したという。
ここからJRの跨線橋を渡り上野桜木二丁目へ至る坂は「御隠殿坂」と呼ばれ輪王寺宮が寛永寺と御隠殿を往復するために設けられたという。御隠殿坂途中の跨線橋は鉄道マニアの聖地となっている。