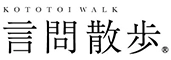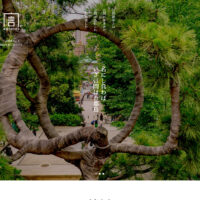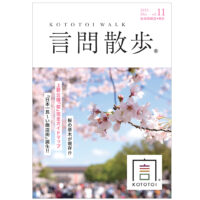夏の風物詩「入谷朝顔まつり」
『朝顔につるべとられてもらい水』万葉の昔から庶民の生活の身近にある朝顔。
江戸の時代には品種改良が進み、色とりどりの花、さまざまな紋様の新種が生まれました。品評会もしばしば開催され、ひところは加熱する人気で投機の対象にもなったりもしました。
入谷はその朝顔の品評会で人気を博した植木師『成田屋留次郎』ゆかりの地で、毎年日本一の朝顔市が開催されています。
朝顔は夏の風物詩としてかかせない存在として、みなさんの心に清涼感という潤いを与えてくれます。そんな親しみやすい朝顔ですが、意外と知らないことも沢山あります。
たとえば朝顔は早朝に花を咲かせますがどうやって朝を感知するのでしょう。どうやら朝を感知するのではなく、暗さを感知する機能があるようで、暗くなってからだいたい十時間後ぐらいに花を咲かせるようです。したがって、蕾に光を当て続けると花は開花しないようです。『暗闇がないと花が咲かない』なんだかちょっと人生訓
を感じますね。
また支柱に巻き付くツルは触感で支柱に当った部分が硬くなり、接していないところが成長するという性質により、巻き付くというメカニズムが生まれるようです。そしてツルはおおむね左巻きでその成長度合いは早く、一時間で支柱をひと巻きするようですから、注意深く観察すると成長していくところが肉眼でもわかるかも知れません。
朝顔市に出かけ、『つるべを取られても優しく見守る人達』の微笑ましい姿を想像しながら、買った鉢植えの朝顔をゆっくり眺めるのも、なにせ贅沢な時間なのですから。